ピアノをひこう

ぼくは別にピアノがきらいじゃない。
練習もいやじゃない。
だけど、
「ピアノの先生やピアニストになるにはもっと練習しないとね」
とこんなふうに言われるのがいやなんだ。
実はぼくはピアノの先生にはなりたくない。
たいてい生徒はあまりやる気がないし、
そんな子たちを教えるのは大変だ。
ピアニストになるなんてそんな大それたことも考えていない。
だからそんなふうにプレッシャーをかけられるといやになってしまう。
1人で家にいるときはこっそりレッスンと関係ない曲をひいたりする。
練習曲もわるくないけど、自分で好きな曲をえらんでひくのは
なにより楽しい。
ある日両親は外出してぼく1人だったから、本だなにかくしてある
がくふを取り出してきてピアノをひき始めたんだ。
ここのところ練習曲があまりうまくひけなくておもしろくなかった
から、よけいに好きな曲をひくのが楽しく感じられた。
ぼくは小一時間ほど気分よくピアノをひいていた。

その時とつぜん母さんが部屋に入ってきた。
ぼくはびっくりしていすから落ちそうになった。
むちゅうでひいていたからげんかんの戸が開くのにぜんぜん
気づかなかった。
母さんは言った。
「きいたことない曲ね。いつ練習してたのかしら?」
ぼくはだまっていた。
「ちゃんとレッスンの曲を練習しないとだめでしょ。
まだまちがえてばっかりじゃない」
―げんかいだ―
「もうピアノはやめる! 次のレッスンはもう受けないよ」
ついに言ってしまった。
今まで何度も言いかけてやめたことを。
母さんはぼくの言ったことをのみこめないようで、
しばらくぽかんとしていたけど、次にぜつぼう的な表情になり、
言った。
「何を言ってるの? 今までがんばってきたのに・・・。
やめるなんてそんなかんたんに決めるもんじゃないわ。
分かってる?」
ぼくは何も言わず母さんの横を通りぬけ外へ出て行った。
いいんだ、これで。
別にピアノがひけなくなるわけじゃないし。
ぼくはそう自分に言い聞かせ、あてもなくぶらぶらと歩いた。
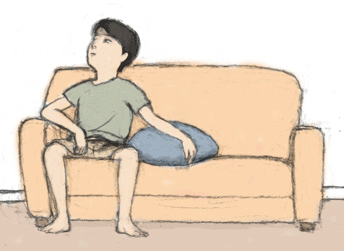
その日は親がるすだったけど、なんかピアノに向かう気が
しなくてソファにすわりボーっとしていた。
トントン。ノックが聞こえた。
ぼくはどこから音がしたのかと思いきょろきょろした。
げんかんまで行き戸を開けてみたけどだれもいない。
トントン。また聞こえた。
ぼくは急にこわくなった。ぼくはおばけなんて信じていない。
だけどこの音は?
ろうかを通って部屋へもどろうとした時、
トントン。
―わかった。音はここからだ。―
ぼくはろうかにかけてあるかがみの前に立った。
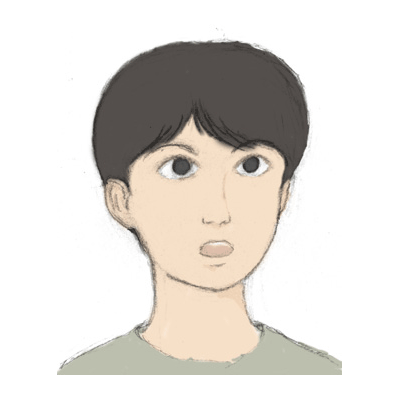
ぜったいここだ。ぼくはかがみにそっと手をのばした。
ぼくの手がふれる前にかがみはまるでとびらのようにそっと
開いた。ぼくは後ずさりした。
こわくてかなしばりにあったように背中をかべにおしつけたまま
目の前に何があらわれるのかを待った。
かがみの向こうにぼくと同じくらいの年の女の子が立っていた。
ぼくは何か言おうとしたけど、あまりの信じられないできごとに
声もでない。
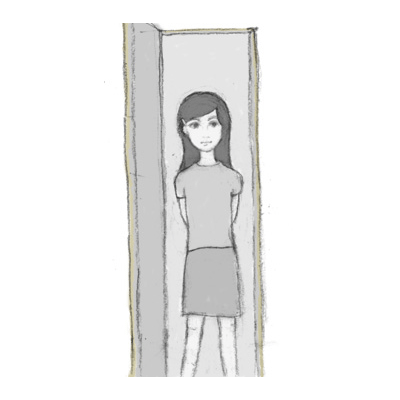
おねがいこわがらないで。私はあなたに言いたいことがあるだけ。
何もしないから」その女の子はそう言った。
ある一つのことをのぞけば、ぼくのクラスの女の子とそうかわりはない。
「きっとそうやってあらわれたんだから、よほど何かわけがあるんだろうね」
ぼくは話せるようになった。
「そうなの。ゆう気がいったんだから。さいきんピアノの音が聞こえないから
心配になって、それであなたと話す決心をしたの」
ぼくは女の子がいがいなことを言い出すのでちょっとおどろいた。
「きみはぼくのピアノをきいてたの?」
「ええそうよ。私の心のささえだったんだから。
毎日あなたがピアノをひくのを楽しみにしていたのよ」
ぼくはふくざつな気持になった。
ぼくのピアノを楽しみにしてくれている人がいたなんて。
「ちょっといろいろあってね。だけどもう二度とピアノをひかないというわけじゃないから」
ぼくがそう言うと女の子はちょっと安心したようだ。
「また、ひいてくれるのね。いつ?今度はいつひいてくれるの?」
ぼくはためらった。家族の手前、当分ひくつもりはないし。
「今日みたいな日ならひけるよ。とうさん、かあさんがいない時。
そうだな1週間に1度か2度くらいかな」
女の子は少しがっかりしたようだった。
「ねえ、ぼくの方からしつ問していい?」
「ええ」
「きみはどうしてそんなにぼくのピアノをききたがってるの?」
「私を見て何か気づかない?」
気づかないわけがない。さいしょに見たしゅんかんから。
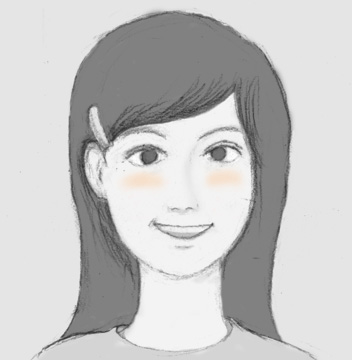
「気づいているよ。じゃあまずそのことについてからしつ問する
よ。どうして君はその・・・白黒なの?」
「私のいるところは色がないの。前はあったんだけど、
いっしょに住んでいた友だちが出て行ってから毎日泣いていたら
だんだん色がなくなってきて、ついに白黒になってしまったの。
その後あなたが引っこしてきて毎日ピアノをきかせてくれたわ。
それが私にとってどれだけすくいになったかわかる?」
ぼくは女の子がとてもかわいそうに思えた。
「何かぼくにできることがあるかな」
「あなたがいやじゃなければ私のところにきてピアノをひいて
くれない?」
「そんなことならかんたんさ」
女の子がはじめてえがおを見せた。すごくうれしそうだ。
その時ぼくは女の子のほっぺがわずかにピンクがかったことに
気づいた。
ぼくがそのことを言おうとした時、げんかんのかぎがさしこまれ
る音がした。
かがみはしずかにしまり、女の子のすがたは見えなくなって
しまった。
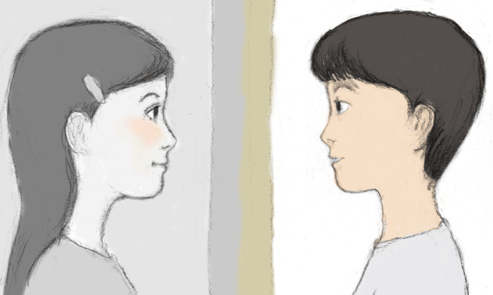
次の日の夜、とうさんとかあさんはコンサートに出かけた。
ぼくは早い夕はんをすますと、かがみの前に行った。
「ねえ、きみ!なまえ聞いてなかったからよびにくいなあ。ねえ、きみ!」
ぼくはノックしながらよびかけた。
かがみは前と同じようにそっと開いた。
女の子が立っていた。
ほっぺはまだ少しピンク色がかっている。
「昨日いいそびれたんだけど、きみのほっぺすこしピンクになっているよ」
ぼくは何よりそれを言いたかった。
「ほんと?」女の子はおどろいた。
「ところで、きみの名前はなんていうの?」
「ナナコ」
「じゃあ・・・ナナコちゃんってよぶよ?」
「いいわ」ナナコちゃんはうれしそうな顔をした。
「あなたの名前は?」
「ぼくは、シンジ。それより今ならナナコちゃんのところへ行ってピアノをひけるよ」
「ほんとなの?うれしいわ。じゃあこっちに来て」
ぼくはちょっとためらった。もしかしてもう二度ともとの世界へもどれなくなるんじゃないだろうかという不安がよぎった。
ナナコちゃんはぼくの不安に気づいたように、
「大丈夫よ。ちゃんとあなたのところへもどれるから」と言った。
ぼくはナナコちゃんの言葉を信じることにした。

かがみの向こうはやはり白黒の部屋だった。
ベッド、勉強づくえ、本だな、ぬいぐるみ、
かばん、なにもかも白黒だ。
しょうじき言って悲しくなってしまった。
さいわいにもアップライトのピアノだけは
その部屋になじんでいる(黒だから!)。
ぼくは気を取りなおしてピアノをひくことにした。
ナナコちゃんはベッドにこしかけ待っていた。
ぼくは少しきんちょうした。
こんなにきたいされるのは初めてだから。
さいしょにしずかな曲をえらんだ。
心をこめてていねいにひいた。

一曲ひき終わったので、ふり向いてナナコちゃんを見た。
泣いている。でもその顔は悲しい顔ではない。
「近くできくともっとすばらしいのね。
ああ、どれだけうれしいかわかる?」
ナナコちゃんはそう言った。ぼくもむねがあつくなった。
こんなによろこんでくれるなんて。ピアノがひけてよかった!
ふと気づくとナナコちゃんの顔全体に色がもどっている。
「ねえナナコちゃん、顔の色がもどってきているよ」
「ほんと?信じられないわ」
「じゃあ、もっとひくよ」
ぼくは今までなかった力が自分の中からわき上がってくるような
感じがした。
ぼくはせんさいでやさしいメロディを、
またきびきびしたいせいのいい音をつぎつぎかなでた。
自分がどこにいるかも忘れるくらいぼっとうしてひき続けた。
何曲ひいただろうか?
手を止め、ふと顔を上げると、水色のかべ紙が目に入った。
次に茶色の木の机、オレンジのクッション。
ぼくは思い切ってナナコちゃんを見た。
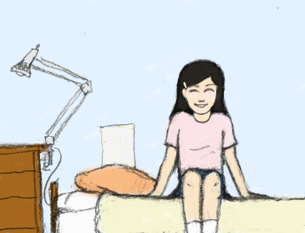
そしてこう言った。
「ナナコちゃんはその方がかわいいよ」
「ありがとうシンジくん」